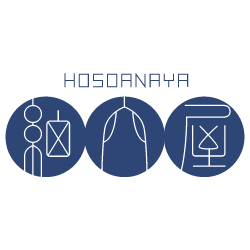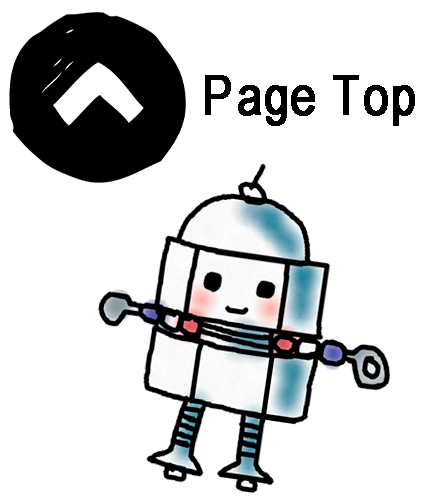毎年、年賀状を送り続けてくれる友だちがいる。私が返信しないにも関わらずである。
返信しなきゃと思いつつも返信せずに数年が経ち、今年こそは!と年賀状を買い、年末年始をバタバタと過ごしてるいちに2月になり、春が過ぎ梅雨になった。「書き損じ葉書」として切手と交換してもらいに郵便局に行くのに、半年もかかった。無駄にしてしまった年賀状の束をようやく手放せる!というスッキリ感。
となるはずが…
「10月から切手代が上がるので、その販売開始日(8月20日)を待って、新しい金額の切手に交換した方が良いですよ」と窓口の女の人が親切に、かつ丁寧に説明してくれた。迷いが生じ、結局年賀状の束を持ち帰った。スッキリ感を期待していただけにモヤモヤ倍増。湿度も重なって、モヤモヤジメジメする羽目に。
ジメジメがモヤモヤを増幅し、「返信しなきゃ」がまた、ふっと頭をよぎる。その日の晩、その友達に思い切って電話した。
お互いに連絡したい、話したいとう同じ思いを抱えながら数年を過ごしていたようである。
「思い切って」に下線を付けたのは、電話するのにエネルギーが必要だったからだ。今電話に出られる状況なのか、電話番号変わってないか、出られなかったとしても折り返してくれるのだろうか、電話するほどの急用は無いけどメールの方がよいか、などコールする前にいろいろと考えてしまう。最終的には声が聞きたい!という思いがエネルギーとなって電話することが出来た。
彼女は彼女で、私に連絡したいと思っても忙しいだろうからとの遠慮もあり、近況を知るためにエストロラボのホームページを覗いてくれたらしい。そこでこのブログを見つけ、毎月楽しみに読んでいると言うのだ!一緒のことで悩んでるんや…と共感することもあるという。SNSを使わない彼女は私がいつブログを更新するかも分からないので、能動的にホームページを見に行くしかないだろうに…。子育て中、仕事もしている彼女の忙しさは、忙しがる私の比ではない(2018年9月ブログ参照)。そんな彼女がブログを読んでくれているなんて、嬉しくって仕方がない。楽しみにしてるというコトバが励みとなり、めったに乗らない筆が乗る感覚♪
毎月恒例の「ブログ書かなきゃ」の焦りを吹き飛ばしてくれた、古き良き友と親切な郵便局員さん。それと連絡を取る気にさせてくれた湿気にも感謝である。